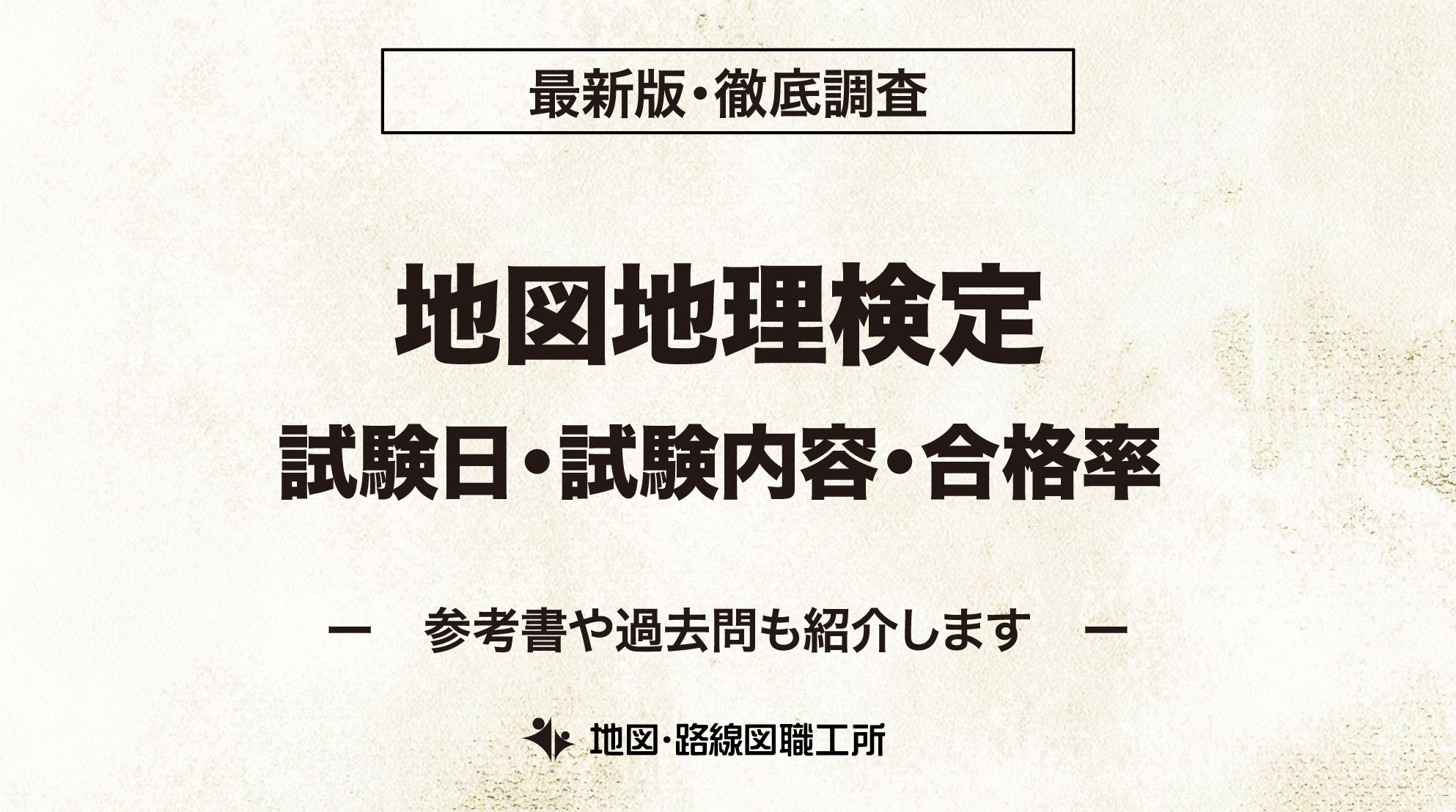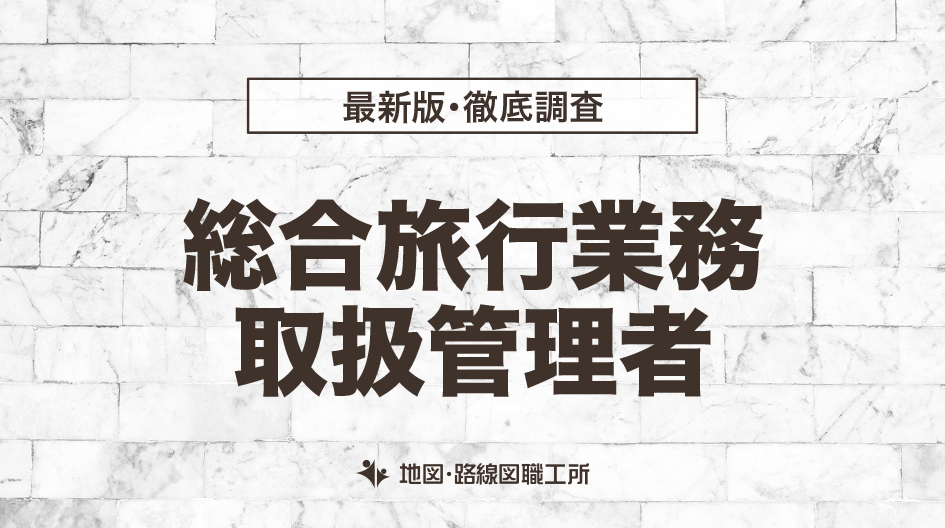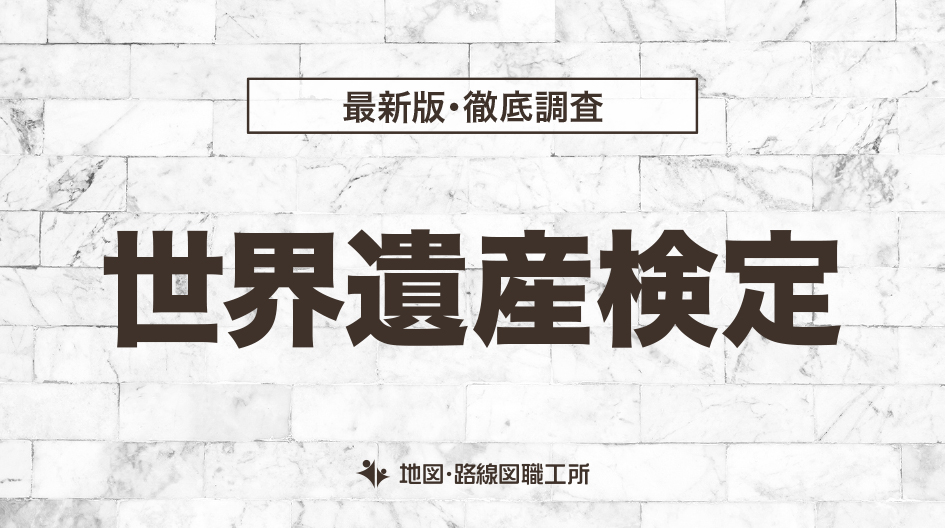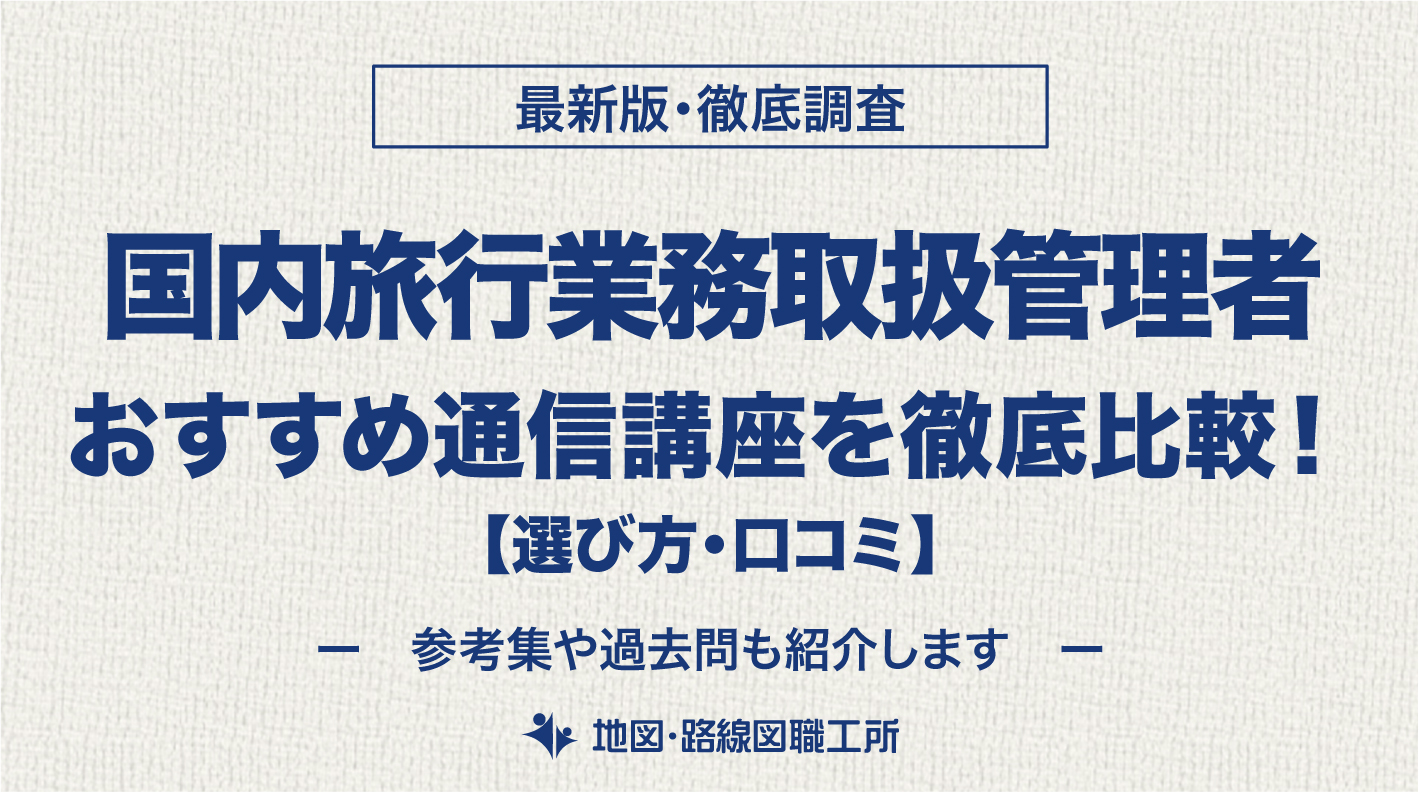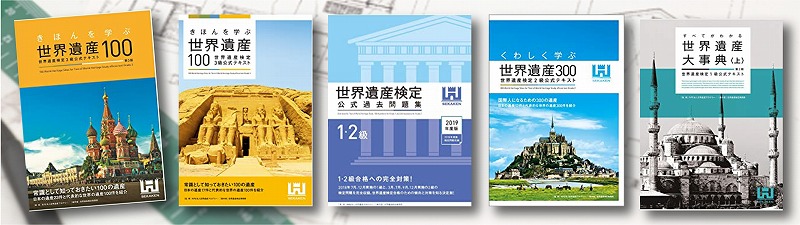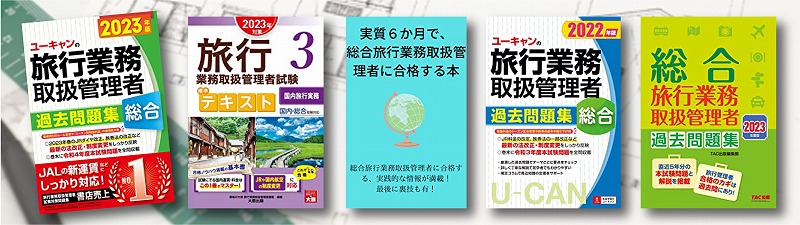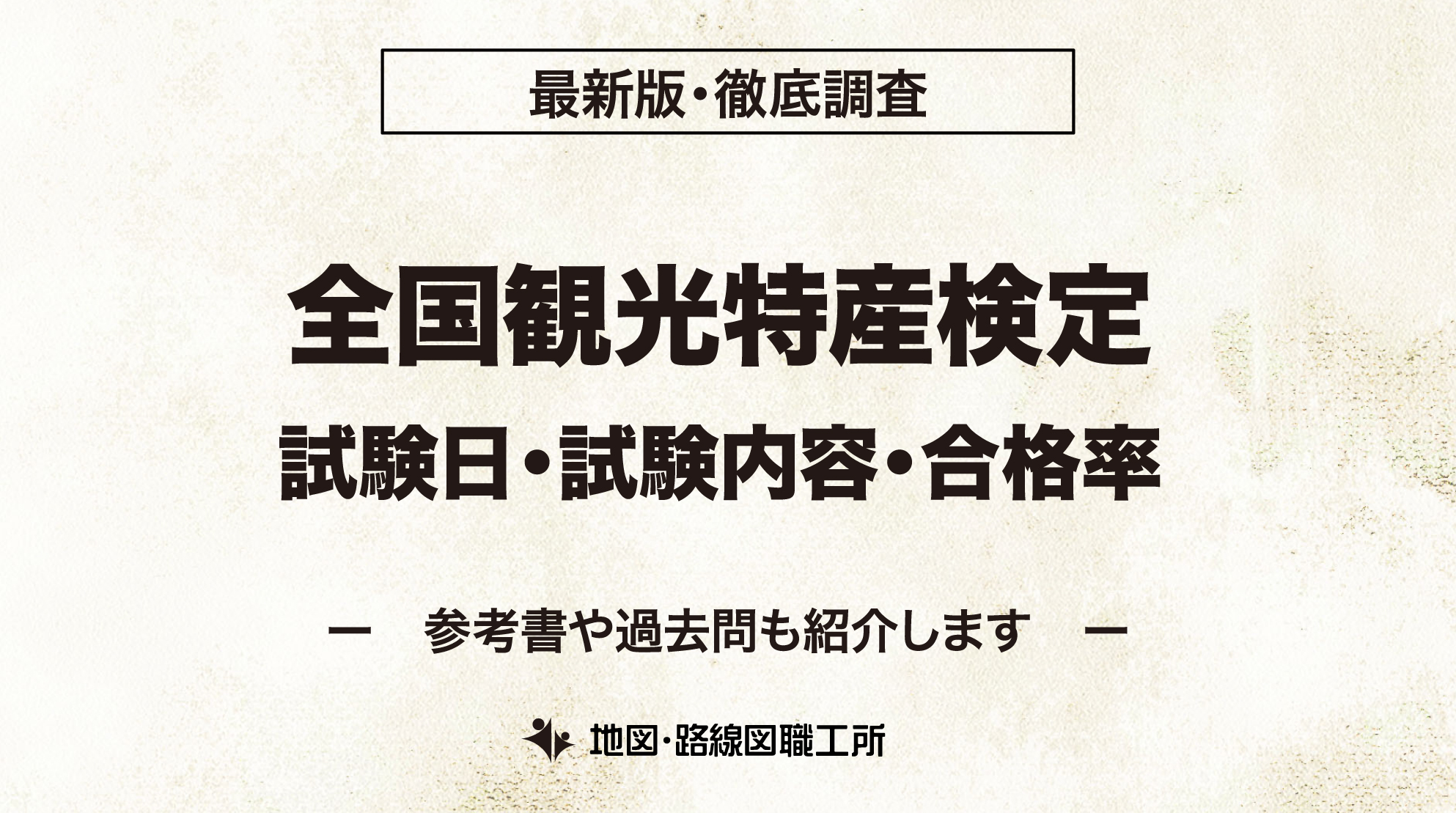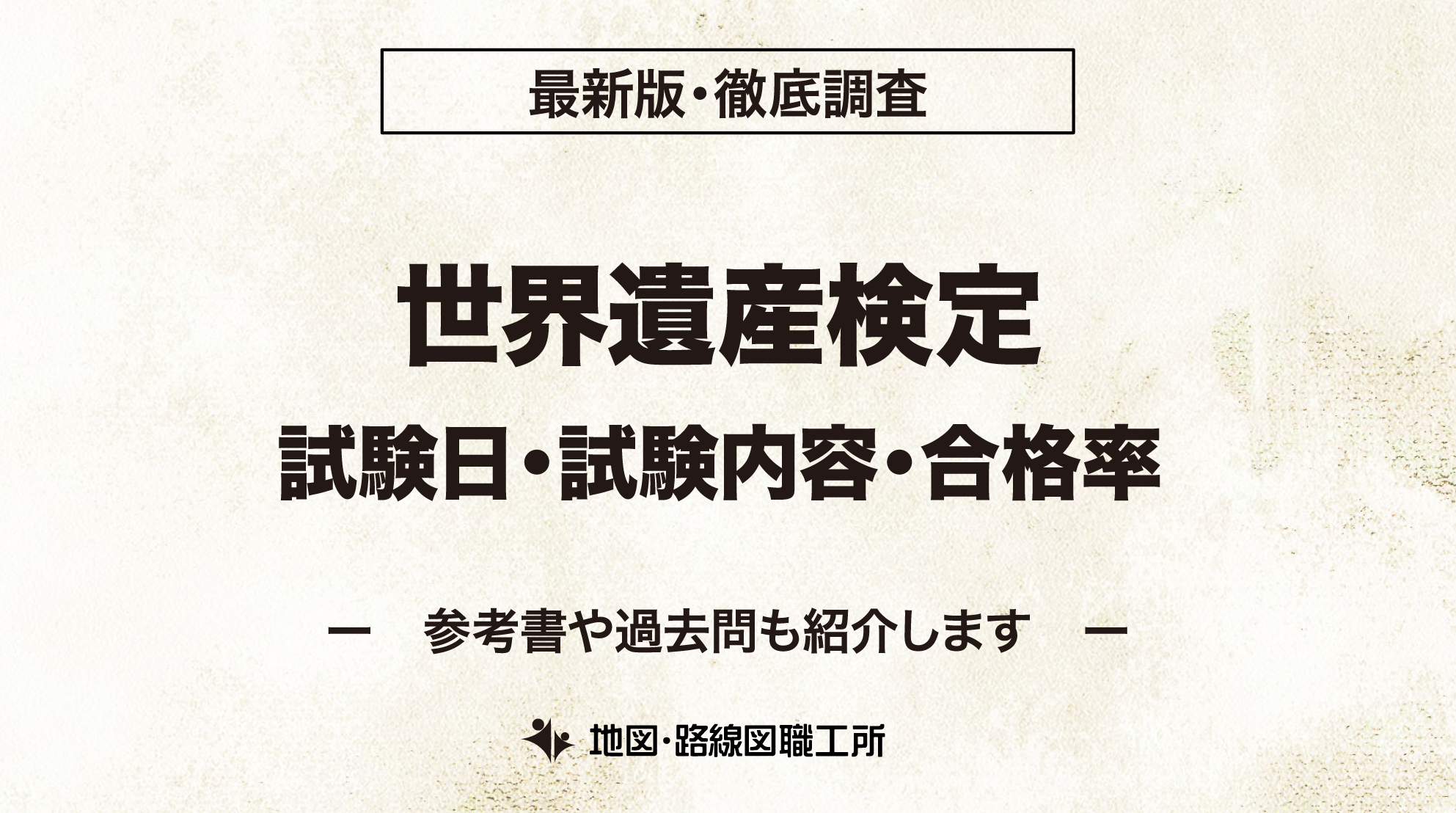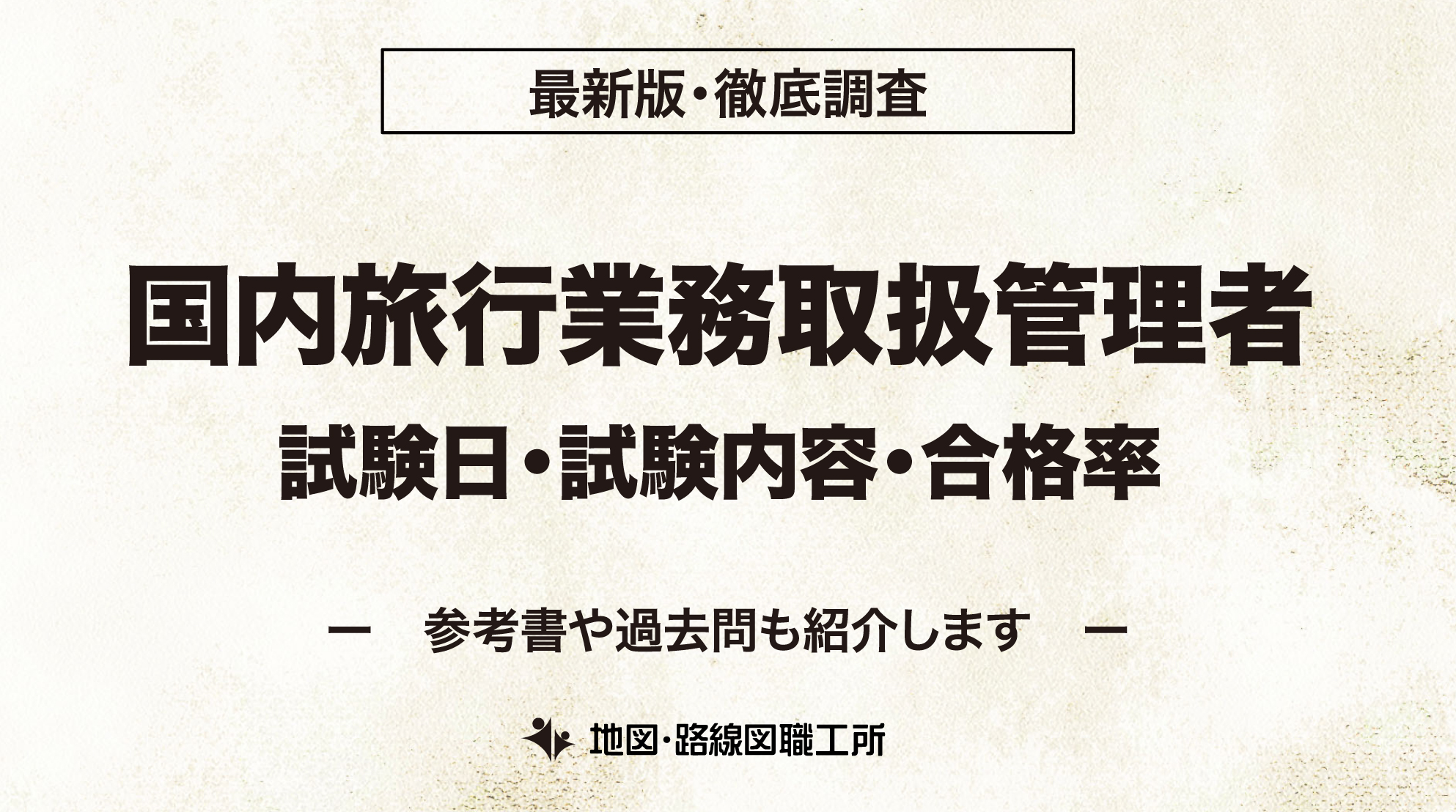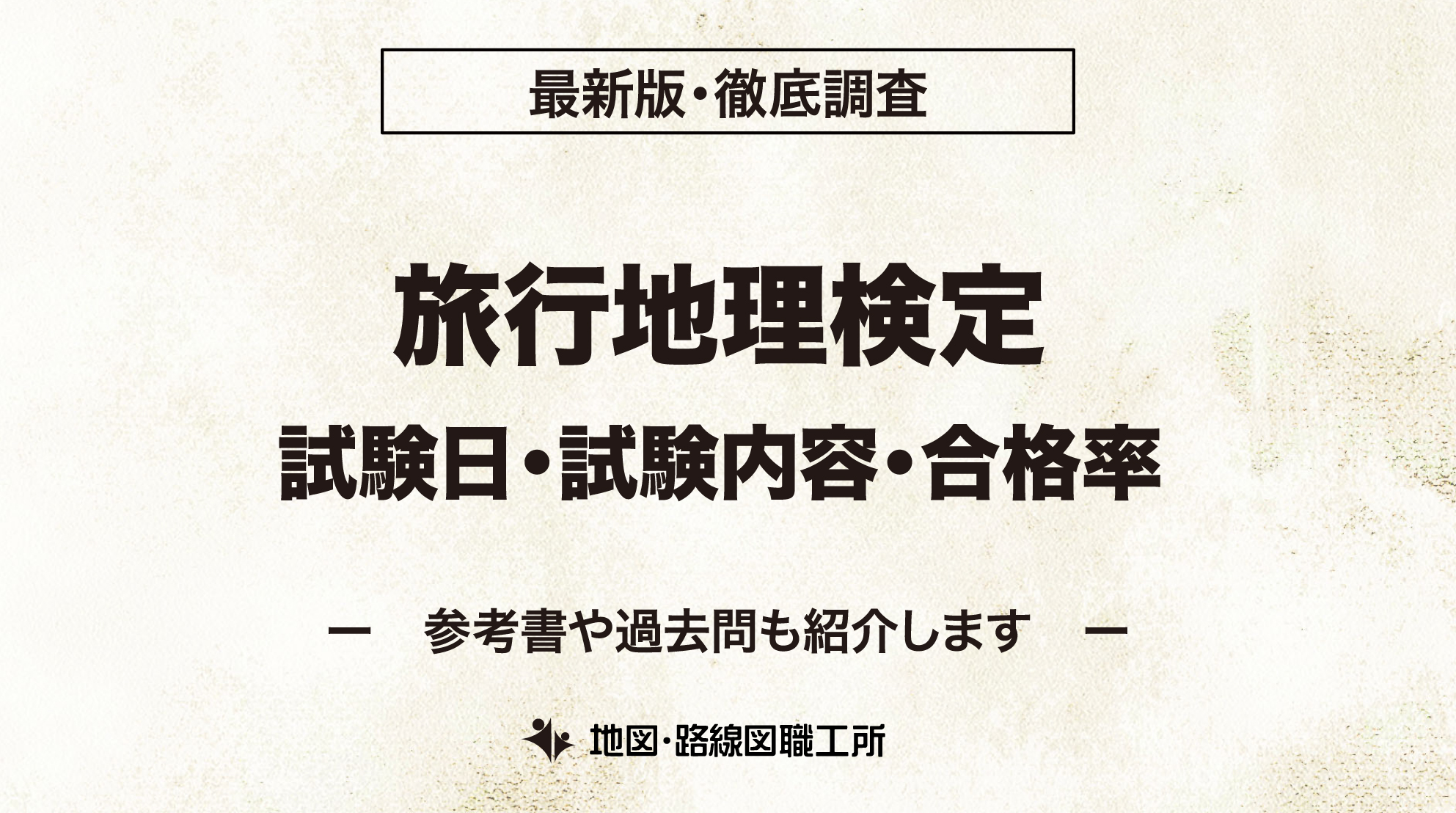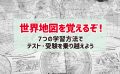この記事では、地図地理検定の試験日・試験内容・合格率についてまとめています。この資格に関心がある皆さま是非参考にしてください。
地図を読んでいればいくらでも時間つぶし出来るという人は案外多いのではないでしょうか。私もその一人です。そんな地図好きに是非おススメなのが地図地理検定です。地図というのは単なる趣味の一分野ではなく、学校での教育指導要領にも含まれる立派な学問です。私立中学や高校、大学受験の勉強の一環になるだけではなく、資格を持っていることが一定の評価基準となることもあります。せっかく知識、頭の中に持っているだけではもったいない。自分の趣味を資格という形で証明してみるのはいかがでしょうか。地図地理検定の概要・試験日程と試験内容、合格率、おすすめの書籍・参考書・過去問をお伝えします。
それでは、地図地理検定について紹介していきましょう。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
地図地理検定の概要・難易度
地図地理検定は、日本地図センターと国土地理協会が共同で実施している民間資格の検定です。実務的な観光地理ではなく、地図の読み方や、地図から景観や自然を予測するなど、より学問的な地理の検定になりますので注意してください。階級は「一般」と「専門」の2種類のみで、「一般」は小中高等学校学習指導要領、過去のセンター試験地理Aなどを参考に作られており、私立中学受験を目指す小学生にもピッタリです。
「専門」は高等学校学習指導要領、過去のセンター試験地理B、国公立二次試験などを参考に作られており、地図好きな中高校生や大学生以上が対象になっています。難関私立中学を目指し、しっかり受験勉強をしている、ないしは受験用の社会の強化が好きな小学生ならば、さほど勉強をしなくても「一般」は合格出来るでしょう。「専門」も同じくで、しっかりと受験勉強をしていれば中学生、高校生でも、さほど難しく感じることはないはずです。非常に普段の地理の学習と密接に関係しているため、多くの学校で受験時に考慮してもらうことの出来る検定です。特に面接のある場合など、漠然と地図が好きというよりも、地図地理検定を取得していると説明した方が、面接官により具体的に伝わり好印象です。ですから、単に検定に合格するだけではなく、なるべく高得点を狙いたいものです。難易度としてはそれほど高レベルではなく受験勉強の一環で受検するにはとてもよいですね。
受験資格
どなたでも受験可能です。特に学生の方は入試のアピールポイントとして活用できます。
受験の申し込み方法
「WEB申し込み」「振替振込申し込み」の2通りがあります。
「WEB申し込み」の場合
- 「検定、受け付けてます」からマイページを登録する。
- マイページへご登録後、「検定、受け付けてます」内の地図地理検定ページの「同意して申し込む」から検定申込画面へ進む。
※受検料の決済方法はクレジットカード決済、もしくはコンビニ決済をお選びいただけます。
「振替払込(ゆうちょ銀行・郵便局)、郵送(現金書留)」の場合
- 「一般財団法人 日本地図センター」の払込取扱票(PDF)をダウンロードし印刷する。印刷環境のない場合は、事務局へリーフレットを請求する。
- 払込取扱票に必要事項を記入する。
- ゆうちょ銀行・郵便局で受験料を支払う。
地図地理検定の試験日程と試験内容
試験日程
2023年11月12日(日)
地図地理検定は例年6月中旬・11月中旬頃に実施されており、願書受付期間は1月下旬~6月上旬頃・6月中旬~11月中旬頃と非常に長くなっています。インターネットからの申し込みも可能です。
試験内容
試験内容は地理に関すること全般で、地図の検定といっても、単に地図記号の暗記や等高線の読み取りだけではなく、社会文化、自然環境、世界地理まで範囲は幅広く出題されます。時事問題や歴史に絡めた問題も扱われており、総合的な地理力を問われます。過去問題はホームページで確認出来ますので、活用してみてください。
出題の目安(一般)
- 一般的な基礎知識を問う問題(教科書レベル)
- 地図の記号・縮尺
- 地形図や空中写真
- 日本の都道府県や市町村
- 世界の国々と都市
- 日本や世界の自然など
出題の目安(専門)
- 地図の投影法
- 測量・地図の基準
- 地図の表現法
- 地図の歴史と古地図
- 空中写真とリモートセンシング
- GIS,web地図
- 地形図の読図・計測
- 主題図と防災・環境
- 世界や日本の地図・地理など
受験手数料
通常料金
| 基礎 | 3,000円(税込) |
|---|---|
| 専門 | 4,000円(税込) |
| 基礎・専門併願 | 5,000円(税込) |
割引料金(リピーター割引・学生割引・シニア割引・地図倶楽部会員割引)
| 基礎 | 2,000円(税込) |
|---|---|
| 専門 | 3,000円(税込) |
| 基礎・専門併願 | 4,000円(税込) |
受験地一覧
札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡 ※各会場の詳細は公式サイトにてご確認ください。
地図地理検定の合格率(合格基準点)
「一般」では100点満点中60点以上が合格となります。「専門」の場合、得点によって1級~3級の資格を得ることが出来ます。この点数は平均点によって前後しますが、
- 概ね80点以上で1級
- 70点前後で2級
- 60点前後で3級
となります。
このほか、96点以上又は1級認定5回で「地図地理力博士」、1級認定3回で「準地図地理力博士」の称号を得ることが出来ます。これは上級地図指導者(マップリーダー)を示すものでもあります。博士の称号を目指して頑張りましょう。合格率は回によって変動がありますが、少なくとも、
- 一般:60%程度
- 専門:1級で10%~20%、2級で20%~30%、3級で40%前後
となっています。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 470人 | 330人 | 70.2% |
| 2021年 | 563人 | 396人 | 70.3% |
| 2020年 | 320人 | 240人 | 75% |
| 2019年 | 498人 | 311人 | 62.4% |
| 2018年 | 518人 | 355人 | 68.5% |
地図地理検定の書籍・参考書・過去問
『地図地理検定の学科試験勉強用のテキスト・問題集ってあるの?』と悩んでいませんか?こちらでは、地図地理検定の学科試験を独学で勉強している方に向けて、おすすめのテキストや問題集をご紹介します。しかし、受験者がそこまで多い検定ではありませんので、参考書はほとんど発売されていません。基本的には学校や塾などで習う範囲ですので、普段から勉強していることをしっかりと定着させていくことが合格への近道と言えるでしょう。
あくまでも地図や地理好きの人がうける検定という意味では、普段の学習に追加で勉強する必要性はあまり感じられません。唯一発売されているのは過去問になりますので、こちらを何度も解いて、自分の弱点を知り、その部分を徹底的に補強してゆきましょう。是非参考にしてみてくださいね。
地図地理検定(一般)過去問集新選100
日本地図センターが発行する唯一の公式テキストです。第24回~第34回から100問を厳選し、6つの分野ごとにまとめ、年度順に配置しています。内容は①地図記号・縮尺関する問題 ②地形図の読み取りや新旧、写真と現地との照合などに関する問題 ③都道府県や市町村に関する問題 ④世界の国々と都市、時差や方位、図法などに関する問題 ⑤日本や世界の自然環境に関する問題 ⑥オリンピックや世界遺産、鉄道の開通などの時事問題です。なお、直近の2年間の過去問と回答は公式ホームページから確認出来ます。
| 著書 | 一般財団法人日本地図センター |
|---|---|
| 出版社 | 日本地図センター |
| ページ数 | – |
地図投影法
公式ページで参考書として紹介されていますが「専門」受験者向けの高度なテキストです。地図製作や測量に必須な投影法の正しい基礎概念と最新の手法をコンピュータを活用しながら説明。3次元の球をどうやって2次元の平面にするか?というテーマについて、数学的見地も交えながら学術的に解説しています。
| 著書 | 政春 尋志 |
|---|---|
| 出版社 | 朝倉書店 |
| ページ数 | 224ページ |

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)